
リード文
「ギルティクラウンって結局どうだったの?」
「途中まで面白かったのに、最終回でがっかり…」
「“ひどい”ってよく言われてるけど、本当にそんなに悪かった?」
SNSや掲示板を見ても、本作の最終回をめぐっては今も激しい賛否が飛び交っています。物語はなぜそこまで評価が分かれるのか?その理由を理解せずに「ひどい」と断じてしまうのは、実はもったいないかもしれません。
筆者はギルティクラウンを放送当時から追い、繰り返し視聴してきたファンの一人です。最初は戸惑いもありましたが、作品のテーマや構造を深掘りしていく中で「この結末にしかできなかった理由」が見えてきました。
この記事では、最終回が“ひどい”と感じられる5つの理由を整理しつつ、作品の再評価につながる視点まで丁寧に解説します。
読み終えた頃には、あなたの中で「ギルティクラウン」の印象が変わっているかもしれません。
——評価が分かれるからこそ、知ってほしい物語があります。
第1章:なぜ「ギルティクラウン」は賛否が分かれるのか?

『ギルティクラウン』は、2011年に放送されたオリジナルアニメであり、放送から10年以上経った今でも「ひどい」「最高だった」と評価が真っ二つに分かれる作品です。
その最大の理由は、物語の前半と後半で作風が大きく変わる点にあります。
前半(1クール目):圧倒的な世界観とスタイリッシュなSF
- 「王の能力=ヴォイド」を手にした少年・桜満集が、葬儀社というレジスタンスに加わり、理不尽な支配体制と戦う
- 作画・音楽ともに完成度が高く、青春SFとして爽快感もある
- ボーイ・ミーツ・ガール的な要素も強く、視聴者の没入感を高めた
後半(2クール目):鬱展開と人間の“業”が中心に
- 主人公が精神的に追い詰められ、仲間同士での裏切りや死別が続く
- サバイバル展開、ウイルス感染、リーダーシップの崩壊など、かなりシリアスな内容に
- 「この展開は誰も望んでいなかった」という戸惑いの声が視聴者に広がった
このように、物語の前半が王道、後半が実験的かつ陰鬱な構成であったことが、評価の分かれ目になったといえるでしょう。
第2章:最終回が“ひどい”と感じられる5つの理由

ここでは、視聴者の間で語られる「ひどい」とされる理由を整理していきます。
1. 結末が救いのないバッドエンドだった
- 主人公・集は右手と右目を失い、ヒロイン・いのりは死亡
- 最終話では誰も報われない展開となり、希望が見えないまま終わる
- 視聴者の期待していた“カタルシス”がなかった
2. キャラクターの行動が唐突で不自然
- いのりの自己犠牲や、涯の真意が描き切れていないと感じる人が多い
- 中盤以降の展開が説明不足になり、「なぜそうなるのか」が伝わらない
- 登場人物の心理描写が浅く、感情移入できなかったとの声も
3. ストーリー展開が複雑すぎる
- 終盤の「ウイルス再拡大」「ダアト」「ロストクリスマス」の設定が詰め込まれすぎ
- 「情報量に対して説明が足りない」という不満が多数
- 一度見ただけでは理解しづらいと感じた視聴者が多かった
4. 主要キャラの大量死
- 校条祭、涯、いのりなど、ファン人気の高いキャラクターが次々と退場
- クラスメイトたちが次々犠牲になる展開も精神的にキツい
- 「こんなに人が死ぬ必要あった?」という声が視聴後に広がった
5. 黒幕の描写が不十分
- 終盤に登場する茎道修一郎(集の父)や真名(姉)など、黒幕キャラの掘り下げが少ない
- 「悪役が勝手に自滅して終わる」という肩透かし感
- 終盤の展開が“説明ではなく雰囲気”で流されたと感じた視聴者が多い
第3章:「それでも心に残る理由」再評価の視点

ギルティクラウンが“ひどい”と酷評される一方で、再視聴した人や年齢を重ねた視聴者の間で「実はすごく良かった」と再評価されることも多い作品です。
再評価のカギは「演出とメッセージ性」
一度目の視聴ではストーリーの急展開や主人公・集の行動に違和感を覚えた人も、再度見直すことで物語に込められたメッセージや演出の巧妙さに気づくことがあります。
- “ヴォイド”という設定:人の心の奥底を武器として取り出す──この設定は、少年少女の心の揺れや他者とのつながりを象徴しています。
- 葬儀社の戦い:単なる戦闘ではなく、“自由と管理”“自我と支配”といった現代的なテーマを背景に持っています。
- ラストのメッセージ性:一見バッドエンドのようにも見えますが、“誰かのために生きること”や“選択の重み”を描いたラストは、深く考察するほど味わいが増します。
視聴者の経験が“受け取り方”を変える
ギルクラは、“感性”によって評価が変わる作品です。10代のときに観て「なんだこれ?」と感じた人が、数年後に再視聴して「めちゃくちゃ刺さった…」と感じるケースも多々あります。
- 人間関係のもどかしさ
- 誰かに依存する弱さと自立への葛藤
- 世界の理不尽さと希望の選択
こうした“成長の物語”は、人生経験を積むことでより深く共感できるようになるのです。
第4章:「キャラクターの魅力と物語構造の深み」

ストーリー展開や世界設定に目が行きがちなギルティクラウンですが、登場キャラクターたちの描かれ方も、物語の奥行きを生み出している大きな要因です。
主人公・桜満集の“弱さ”と“成長”
集は典型的な“ヘタレ主人公”として批判されることもありますが、実はこの“ヘタレ具合”こそが彼の魅力であり、物語の主軸です。
- 最初は他人任せで流されるだけの存在
- しかし大切な人との出会いや喪失を通じて“王の力”と向き合っていく
- 最終的には自分の意思で“選び、背負う”決断を下す
「完璧じゃない主人公」が、自分なりの正義と向き合いながら成長する──その姿は、現代の不安定な若者像に通じるものがあります。
ヒロイン・楪いのりの“人間らしさ”
いのりはクールビューティー系のヒロインに見えますが、物語が進むにつれてその“心の揺れ”や“感情の芽生え”が丁寧に描かれていきます。
- 任務として動いていた彼女が、徐々に“集という存在”に心を開いていく
- 戦いの中で迷いや恐れを見せながらも、自分なりの意思を持ち始める
- ラストでは「誰かのために生きること」を選ぶ
彼女の変化は、感情を持たなかった存在が“人間”になっていくような過程そのものであり、強く印象に残ります。
キャラの役割が物語構造に組み込まれている

ギルクラのキャラクターたちは、ただの“味方”や“敵”として登場するのではなく、それぞれがテーマを象徴する存在として配置されています。
- 涯(ガイ):理想を体現するカリスマ的存在だが、支配と自由の狭間で揺れる
- ツグミや綾瀬:葬儀社のメンバーとして生きる中で、個々の信念や想いが描かれる
- 嘘界(ウソカイ)や茎道:裏切りや欲望といった“負の感情”を象徴するキャラ
物語に登場するキャラそれぞれが、“人間の可能性と限界”を提示しており、構造的にも深い仕掛けとなっています。
ギルティクラウンは、ストーリー全体を俯瞰して観ることで、キャラクターたちの配置と成長、役割に込められたメッセージ性がじわじわと浮かび上がってくる作品です。
単なる青春SFアニメにとどまらず、“生きるとはどういうことか”という問いをキャラを通じて投げかけてくる── そんな“奥深い構造”を持つ作品として再評価される理由がここにあるのです。
第5章:音楽と映像演出が名作と呼ばれる理由

音楽と映像演出が名作と呼ばれる理由
『ギルティクラウン』は、ストーリーの好みが分かれる作品ですが、音楽と映像演出に関しては、ほとんどの人が「文句なし」と評価しています。
作品全体の印象を決定づけるほど、この2つの要素がとにかく強いんです。
見始めた瞬間に引き込まれる、圧倒的な映像美

公式サイトギルティクラウン [ GUILTY CROWN ]より
まず特筆すべきは、アニメーションのクオリティとカメラワークのダイナミックさです。
- 背景美術のリアルさと色彩のコントラスト
- アクションシーンにおける高速カットと立体的な動き
- ライトの使い方や、静と動の緩急を活かしたシーン演出
特にヴォイド発動時の演出は毎回テンションが上がるほどスタイリッシュで、「これを観るために観てる」と言う人がいてもおかしくないレベルです。
制作は『攻殻機動隊』『PSYCHO-PASS』などを手がけたProduction I.G。その技術力が惜しみなく注がれています。
主題歌・挿入歌が作品の世界観と完全に融合している
本作のもう一つの大きな魅力が、supercellとEGOISTによる音楽の力です。
OP:supercell「My Dearest」
- 1話の冒頭からこの曲に心を掴まれた人も多いはず
- “希望と哀しみが交錯する”ような歌詞とメロディが作品のテーマと一致
ED:EGOIST「Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜」
- 本編の余韻を受け止めてくれる、切なく美しい一曲
- 実は劇中のバンド「EGOIST」のボーカル=ヒロイン・いのりという設定
他にも、挿入歌「The Everlasting Guilty Crown」や「Planetes」など、曲が流れるだけで感情を揺さぶられる場面が何度もあります。
音と映像が“感情を支える”演出になっている

公式サイトギルティクラウン [ GUILTY CROWN ]より
たとえば、集が誰かのヴォイドを引き出すシーンでは、
音が一度スッと静まり、重低音とともに心臓を打つような効果音が入る——。
そこにカメラワーク、人物の表情、そして挿入歌が重なって、
視聴者の「感情の波」を音と映像で押し上げてくるんです。
「物語を“見せる”のではなく、“感じさせる”」
そんな演出が毎話のように詰め込まれているのが、ギルティクラウンの凄さです。
まとめ:ギルティクラウンの音楽と映像は、アニメ史に残るレベル
- 音楽とアニメーションが完全に連動している
- 映像そのものが“感情の演出装置”として機能している
- 主題歌・挿入歌が単なるBGMではなく、物語の一部になっている
ストーリーに対して「合わなかった」と感じる人でも、音楽と映像の美しさに関しては納得せざるを得ない完成度。
これが“名作”と呼ばれる理由のひとつです。
第6章:「印象的な名言・名シーンで振り返る」

『ギルティクラウン』には、賛否を超えて**「これは忘れられない…」**と思わせるシーンやセリフが数多く存在します。
音楽や映像だけでなく、「言葉の重み」や「演出のタイミング」が絶妙にハマるからこそ、胸に残る瞬間が生まれるのです。
桜満集の「友達を武器に戦う──それは僕が戴きし、罪の王冠」

作品を象徴するキャッチコピーであり、主人公・桜満集の運命を表す一文です。
印象的な名言
「友達を武器に戦う。 それは僕が戴きし、罪の王冠」
それは、信頼と裏切り、希望と罪のすべてを背負った彼の物語そのもの。
一見中二病的に聞こえるこのセリフも、物語を見終えた後だと、
“ああ、あの苦しさをすべて込めた言葉だったんだ”と納得させられます。
校条祭の「優しい王様になってね」

物語中盤、集の心を支えていたクラスメイト・祭(まつり)が、命を落とす前に遺した言葉。
印象的な名言
「ねぇ、集、“やさしいおうさま”って絵本、読んだことある?
その王様は、とっても優しくてね、みんなにお金をあげたり、土地を譲ったりしていたら、とうとう国がなくなってしまったの……
王様はみんなに怒られちゃうんだけど、でも私は、そんな王様が大好きだった……。たぶん……私の初恋
集はその王様に似てるの。優しくて、損しちゃうところが……。私ね、集はきっといい王様になると思うなぁ
集……よかった……。集に……あげる。私の……」
このセリフは、集にとって最後まで背負い続ける“願い”となり、
そして視聴者にとっては、“もう二度と戻らない日常”を実感させる名言でもあります。
祭のヴォイド(回復型)と性格を重ねると、
彼女こそ“癒し”と“人間味”を象徴するキャラだったことがよく分かります。
楪いのりの「やればできるかもしれない。でも、やらないと絶対にできない」
終盤、集が迷いの中にある時、いのりが静かに伝えたセリフ。

印象的な名言
「やればできるかもしれない。でも、やらないと絶対にできない」
これは、どんなに不安でも、どんなに怖くても、
“一歩を踏み出さなければ何も変わらない”というメッセージ。
控えめで自分を押し殺していたいのりが、
“自分の言葉で”伝えたこのセリフには、彼女の大きな成長と強さがにじんでいます。
涯の最後の選択と、静かな別れの演出
終盤、涯は王の力を再び集に託し、自らの命を終える道を選びます。
この場面に台詞はほとんどなく、
音楽と静かな演出だけで“すべてを悟った者同士の別れ”が描かれるのが印象的。
派手なセリフよりも、
「語らずに伝える」静かな演出が視聴者の想像力を刺激し、余韻を残してくれるのです。
シーンと音楽が一体になった“感情の爆発”がある
- ヴォイドを引き出す瞬間のスローモーション
- 裏切りが発覚する瞬間のカメラ演出
- キャラが命を落とす瞬間に流れる挿入歌
こうした**“感情のピーク”に合わせた演出設計**が、視聴体験をより強烈なものにしています。
ストーリー構造には疑問を持ったとしても、
これらの名シーンが“忘れられないアニメ”という印象を残してくれるのです。
まとめ:名言・名場面があるからこそ、何度も思い返したくなる
- 一言で心を打つセリフの数々
- キャラの生き様を象徴する最後の言葉
- 演出と音楽が融合した心揺さぶる場面
『ギルティクラウン』には、その瞬間だけで心を奪われる力があります。
そしてそれこそが、作品が“賛否の枠を超えて語り継がれる理由”なのかもしれません。
第七章「用語解説|世界観や設定の整理」
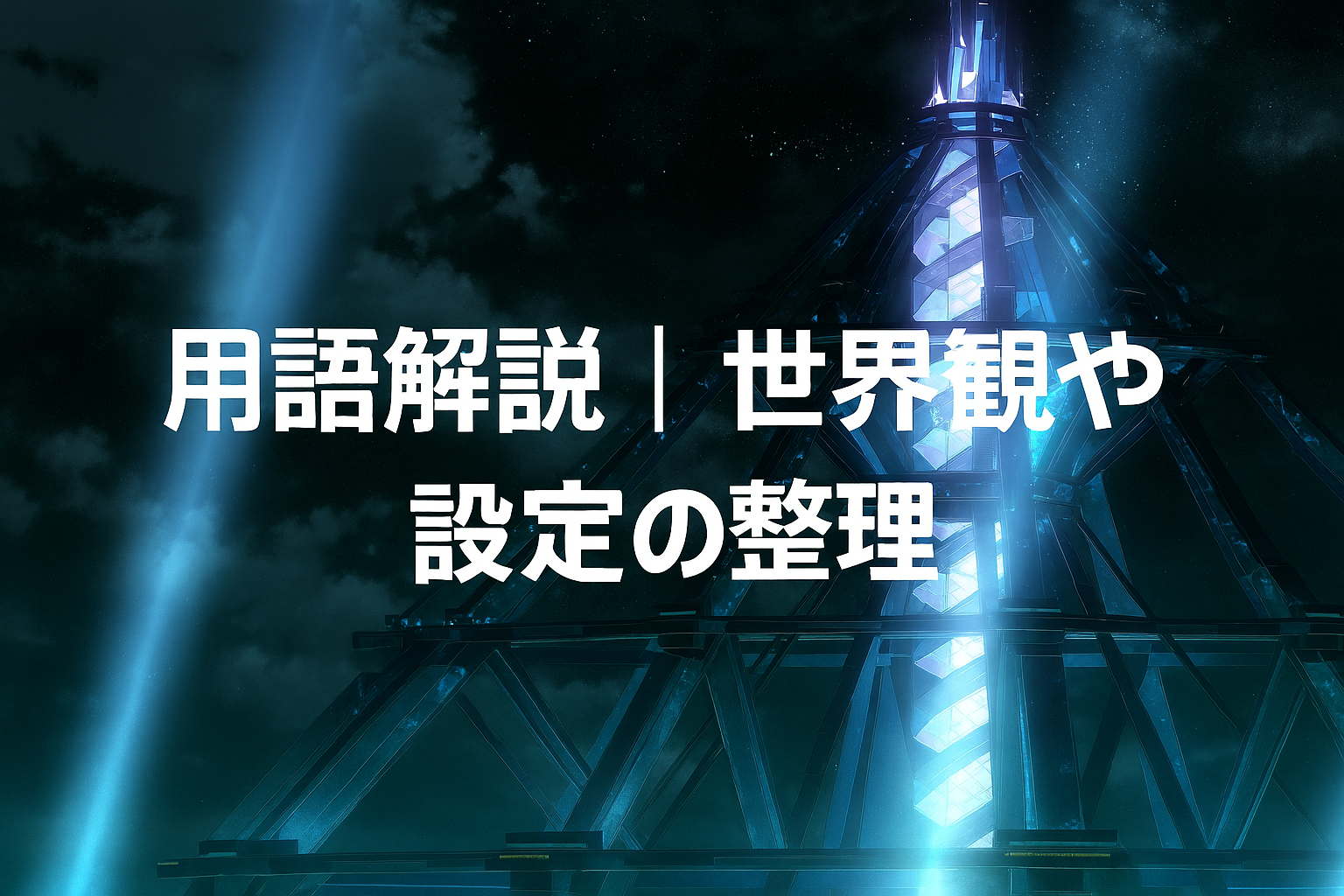
用語解説|世界観や設定の整理
『ギルティクラウン』は魅力的なビジュアルと音楽に引き込まれる一方で、専門用語や設定がやや複雑に感じる人も多い作品です。
ここでは、物語を理解するうえで重要なキーワードを、できるだけやさしく解説します。
ヴォイド(Void)

物語の根幹を担う“王の力”。
桜満集が手にした能力で、他人の「心の本質」を武器や道具として引き出す力です。
- ヴォイドは人によって形が異なる(例:剣、盾、楽器、回復アイテムなど)
- 基本的に16〜17歳の未成年からしか引き出せない
- 持ち主の感情や精神状態によって性能が変化することもある
つまり、「その人がどんな人間なのか」が“形”になって現れるのがヴォイド。
この設定そのものがキャラクター描写に直結していて、作品のテーマ性を深めています。
アポカリプスウイルス

人間の体を“結晶化”させて死に至らしめる謎のウイルス。
- 日本で大流行し、国家崩壊の原因になった
- 感染者の感情や精神状態が発症と関係しているとされる
- 単なる病気ではなく、人間の進化や存在意義に関わる「神の病」とも
このウイルスをめぐる戦いが物語の中核であり、最終的には「人類の存続」や「生きる意味」にまで踏み込むテーマになります。
ロスト・クリスマス

2029年12月24日に起きた日本壊滅のきっかけとなる事件。
- アポカリプスウイルスが初めて大量発生
- 主人公・集の過去や家族の秘密とも関係が深い
- この事件をきっかけに、日本はGHQによる統治下に置かれる
物語序盤では詳細が語られませんが、終盤に向けてこの事件の真相が明かされていきます。
GHQ(Global Health Organization)

ロスト・クリスマス後、日本を“保護”という名目で支配する国際組織。
- アメリカを中心とした対策組織という設定
- 表向きは復興支援だが、実態は軍事占領に近い
- ギルティクラウン世界における“圧政”の象徴
集たちが参加する“葬儀社”は、このGHQに反旗を翻すレジスタンス組織です。
葬儀社(Funeral Parlor)

物語序盤で集が関わることになる反政府組織。
- リーダーは恙神涯(がい)
- 表向きはテロリストだが、真の目的はアポカリプスウイルスの真相解明と自由の奪還
- メンバーは個性的で、後に主要キャラとして活躍する人物も多い
いのりもこの葬儀社のメンバーで、集との出会いもこの組織を通じて始まります。
ヴォイドゲノム

「王の力」を宿すための遺伝子薬(カプセル状)。
- これを体内に取り込むことでヴォイド能力を得られる
- 集や涯がこの力を得る鍵となった
- 複製や暴走もあり、世界を揺るがす存在に
このカプセルをめぐって物語が大きく動き出す場面もあり、重要なガジェットです。
まとめ:設定を知れば、物語の深さが見えてくる
- 難解に見える用語も、キャラやストーリーに深く関わっている
- 設定そのものが「テーマ」を表している(例:心=ヴォイド、進化=ウイルス)
- 覚えなくても楽しめるけれど、知っていると“解像度”が一気に上がる!
ギルティクラウンは、「人間とは何か」「他者とどう向き合うか」を、こうした設定を通じて描こうとしている作品です。
もし最初に“意味が分からなかった”と感じた方も、改めて見返すと見え方がガラッと変わるかもしれません。
第8章:「再視聴で気づく仕掛けと伏線」
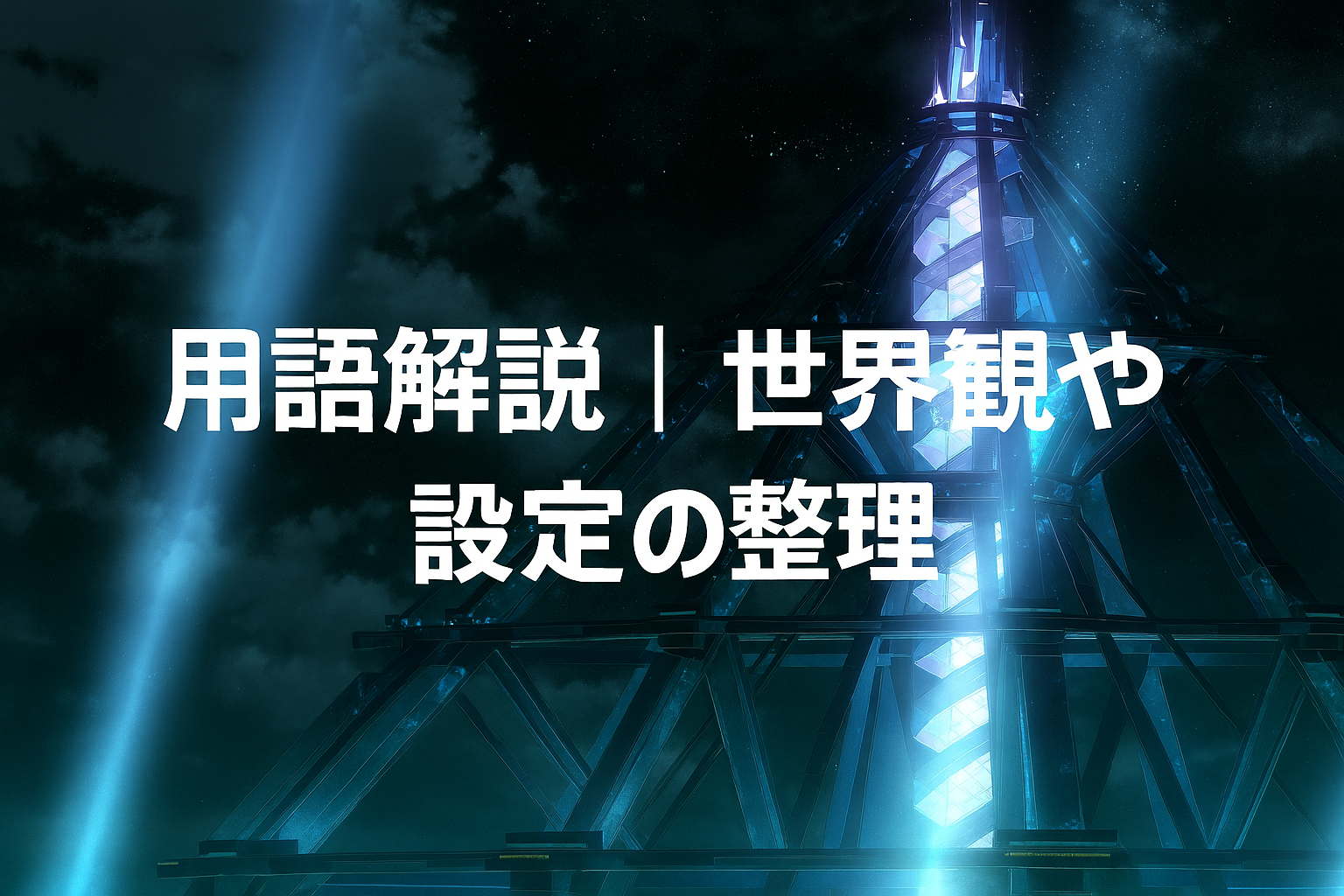
再視聴で気づく仕掛けと伏線
『ギルティクラウン』は、一度目の視聴では「展開が早すぎる」「よく分からなかった」と感じてしまう人が少なくありません。
しかし、改めて見返すと「あのセリフには意味があったのか」「あの演出、伏線だったんだ」と気づくシーンが数多く仕込まれている作品でもあります。
1. 涯の行動や言動の“違和感”が、実は全て伏線だった
物語序盤、涯の言動にはどこか“裏がある”ような雰囲気が漂っていました。
無言で集に命令したり、いのりに命じて動かせたり──「本当に味方なのか?」と感じた視聴者もいたはずです。
しかし終盤、涯の過去と「ロスト・クリスマス」の真実が明かされることで、彼の行動すべてが**“仲間や世界を守るための遠回りな選択”だった**ことが分かります。
▶︎ 再視聴ポイント
1〜3話の涯のセリフは、すべて“未来を見据えていた者の言葉”に変わる
2. ヴォイドの“形”がキャラの本質を映している
初見時は「かっこいい武器だな」で終わりがちなヴォイドのデザインですが、
再視聴すると「キャラの心がそのまま表れてるんだ」と深く納得できます。
- 祭のヴォイド=他者を癒すバンドエイド型 → 彼女の“献身”の象徴
- いのりのヴォイド=斬撃武器 → 内に秘めた強さと決意の現れ
- 綾瀬のヴォイド=足に装着する補助装置 → 失った自由を“戦いで取り戻す”意思の象徴
▶︎ 再視聴ポイント
ヴォイドは「このキャラは何を大切にしているのか?」を読み取る手がかりになる
3. いのりの「感情の変化」も、微細な描写で表現されていた
いのりは序盤、「感情のない人形」のように振る舞っていました。
しかし集との関係が進むにつれ、視線、声色、仕草に“人間らしさ”が徐々に現れていきます。
特に注目したいのは、第1話と第10話以降の目線の使い方や会話のテンポ。
無表情に見えるシーンでも、実は「目をそらさない」「一瞬口角を上げる」など、細かな演出が心情変化を示しています。
▶︎ 再視聴ポイント
いのりの変化は“感情のセリフ”ではなく、“無言の演技”で語られている
4. 結末につながる“意味深な演出”が前半から登場している
例えば、第3話で集が「本当のリーダーってなんだろう…」とつぶやくシーン。
このセリフは、後の“暴君化”と“贖罪”への大きな伏線となっており、脚本の狙いが読み取れるポイントです。
また、終盤に集が「王の力をもう一度手にする」展開も、1クール目の中盤に伏線が張られており、
細かな描写やセリフが“2周目視聴”でつながっていくように作られています。
▶︎ 再視聴ポイント
集の成長や“王としての在り方”は、最初からテーマとして提示されている
まとめ:2回目の視聴で“本当のギルティクラウン”が見えてくる
- 登場人物の裏にある意図や背景
- セリフや演出に隠された伏線
- ヴォイドに込められた心の形
- 無言の演技が語る感情の機微
ギルティクラウンは、「派手な展開」に目を奪われがちですが、実は内側に緻密な感情描写とテーマ性が織り込まれた作品です。
初見では“置いてきぼり”を感じた人も、再視聴すればその印象が180度変わる可能性があります。
むしろこの作品は、「2回見ることを前提に作られている」とさえ感じるほど。
第9章:「ギルティクラウンが刺さる人・刺さらない人」
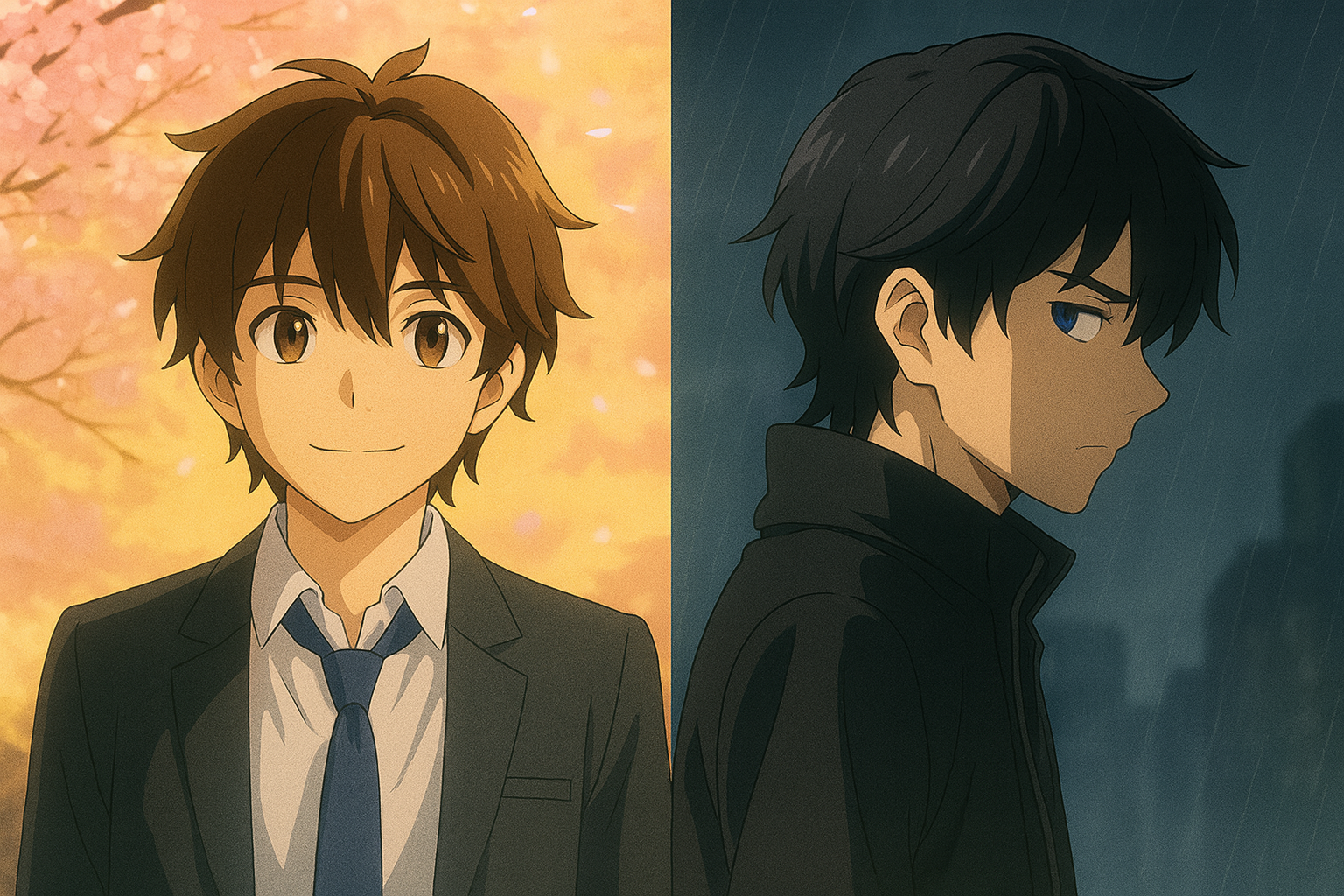
ギルティクラウンが“刺さる人”・“刺さらない人”の違いとは?
『ギルティクラウン』は、放送当時から**「神アニメ」とも「残念アニメ」とも評価が分かれる珍しい作品**でした。
なぜこんなにも評価が二極化するのか?その答えは、「何をアニメに求めるか」という視聴者の価値観にあります。
刺さらない人:物語のロジックや整合性を重視するタイプ
ギルティクラウンが合わなかったという人に多いのが、次のようなタイプです。
- ストーリー展開に“説得力”や“整合性”を求める
- ご都合主義的な展開やキャラの行動理由が曖昧だと冷める
- 主人公の葛藤や成長がしっかり描かれていないと感じると厳しい
確かに、ギルクラはキャラの心情変化の描写が急だったり、設定が回収しきれていないと感じる部分があるため、ロジック重視の視聴者には“粗”が目立ってしまうのも事実です。
刺さる人:感情や演出・世界観の没入感を重視するタイプ
逆に「ギルクラ大好き!」という人は、こんなところに魅力を感じています。
- 映像と音楽が生み出す“世界観”に惹き込まれた
- キャラの葛藤や関係性に共感できた
- 美しい演出と心を揺さぶるBGMに感情が揺れた
ストーリーの整合性よりも、「熱さ」や「切なさ」、「演出が心を動かしてくれるか」に重点を置く人には、ギルクラはドンピシャで刺さるのです。
特に10〜15歳前後に観た人には、思春期特有の感情に寄り添ってくれた“青春の一本”として強く残っているケースも多いです。
あえて言おう、「どっちの意見も正しい」
ギルティクラウンは、アニメの“どこを重視するか”で評価が大きく変わるタイプの作品です。
脚本構成だけで評価すれば粗が目立つ一方で、
「演出・音楽・キャラクター・テーマ性」のレイヤーで見ると、唯一無二の輝きを放っている──。
この“極端な評価差”そのものが、ギルクラという作品の個性であり、
それだけ人の心に強く残るパワーがある証拠でもあります。
まとめ:ギルクラは“好き嫌いがはっきりする、だからこそ語りたくなるアニメ”
- ストーリーの整合性や展開の丁寧さを求める人には合わないかも
- でも、演出・音楽・キャラの感情に共鳴する人には深く刺さる
- 良くも悪くも、観る人の“感性”を試されるアニメ
“名作かどうか”は、人それぞれの基準によって変わります。
ギルティクラウンは「万人にオススメできる」作品ではありません。
でも、「自分にとっての特別な一本」と感じられたら、それはもう立派な“名作”です。
【総まとめ】ギルティクラウンという作品の魅力とは?

『ギルティクラウン』は、脚本構成やキャラの行動に疑問を持つ声も少なくありません。
しかし、それでもなお“心に残るアニメ”として語り継がれる理由があります。
それは──
- 心を揺さぶる音楽と映像美
- 感情の機微を映す演出と世界観
- 「罪」と「王冠」というテーマを貫くラストまでの流れ
- 思春期の葛藤を重ねたキャラクターたちの成長
この作品は、“アニメに完璧な構成”を求める人には刺さらないかもしれません。
でも、“感情で動くドラマ”や“演出で魅せるストーリー”が好きな人には、深く刺さるはずです。
物語の整合性以上に、「なぜだか何度も思い出してしまう」──
そんな“忘れられない体験”こそ、ギルティクラウンの魅力なのかもしれません。
🎬 あなたはどう感じましたか?
『ギルティクラウン』について、あなたの感想や好きなシーンがあればぜひコメントやSNSで教えてください!
📣感想・考察・共感ポイントなど、どんなことでも大歓迎です!
🔁 この記事が役に立ったら、ぜひX(旧Twitter)などでシェアしていただけると嬉しいです。
📚 また、当ブログでは他のアニメやアニメスロット機の考察・レビューも掲載中!
気になる方はトップページまたは関連記事もぜひチェックしてみてください。
👇あわせて読みたい記事はこちら:
- 【L東京喰種】地域密着ホールの“ご当地グール”をリセット狙いで実践
- スマスロ【L東京喰種】「喰うか喰われる」が面白い実践データ・感想 パート1
- 【東京喰種】トーカ(霧嶋董香)が”可愛いと言われる”理由と魅力4選|名シーンを解説
- 【スマスロ L東京喰種】機種解説の決定版!実戦の声から人気の理由、重要ポイントを完全網羅
- 【2025年版】パチスロからアニメへ!『東京喰種』の世界観を120%楽しむ方法
最後までお読みいただきありがとうございました!
あなたの“記憶に残るアニメ”になったなら、
それだけでギルティクラウンは、“あなただけの名作”です。


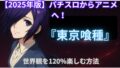
コメント